西村幸祐『1980年代』(育鵬社)を読んだ。
2012年に出た『幻の黄金時代 ―オンリーイエスタデイ’80s』(祥伝社)の加筆・訂正したものです。
旧版は「オンリーイエスタデイ」に魅かれて発売後すぐに買って読んだ。アレンの『オンリーイエスタデイ―1920年代・アメリカ』を筑摩叢書で読んでいたから80年代をこう呼んだ西村さんの絶妙な副題に共感を覚えていた。ちなみにアレンの本は80年代の半ば(だと思う)教師になりたての頃に読んでとても触発された。
第1章はこう始まる。
「かつて日本が眩い宝石のように輝いていた時代があった。キラキラと極彩色の光を放ち,その煌めきは回転するレーザービームのように、極東アジアの一角から世界の隅々を照らし出すかのようだった。日本が発信するあらゆる<情報>が世界に刺激を与え、特に文化と経済の分野で影響を及ぼしていた。といってもこれは戦前の話ではない。つい二昔前の、80年代の日本の姿だった。
オイルショックの危機を持ち前の勤勉さと克己心で乗り切った日本人は、エズラ・ヴォ―ゲルが『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(弘中和歌子訳 阪急コミュニケーションズ)という少々こそばゆい書物を著した昭和55年(1980)から、世界のナンバーワンを目指す新しい時代に突入していた」
時代の気分はプロローグのこんな要約がよくわかります。
「明るく、そして猥雑で、透明感と開放感があった時代。躁状態で走り回り、片っ端から仕事をこなし続けても、次々と新しい仕事が舞い込んでくる。そんなトランス状態の中で、未来がどこまでも開けていたと、誰もが錯覚した時代。それが80年代だった」
しかし、そういう80年代に「実はポッカリと大きな暗い穴が見えない場所に開いていた」。絶頂期の日本の裏側に。現在の日本の重大な危機を読み解く鍵が隠されていたというのが本書のもう一つのテーマです。
新版では書名から「黄金時代」というタイトルが消え、序章「失われた三十年とは何か」と終章「失われた三十年への訣別」が強調されて、より後者のテーマが前に出るつくりになっている。間違っているかもしれないがそういう印象を持った。もちろんそれと「訣別する」ためです。
この時代に著者は音楽雑誌やF1、サッカーWCなどの編集者やジャーナリストとして活躍されたので、そのあたりのことが生き生きと描かれている。それと村上春樹の評価がいい。文学では80年代はまさに村上春樹の登場で大きく動いた時代だった。先日お亡くなりになった福田和也がのちに「小説界は村上春樹とその他大勢の時代になった」と書いていました。
80年代の「暗い穴」のほうの代表は、「国民に隠されてしまった」北朝鮮拉致問題と中国・韓国による歴史情報戦でこれがやがて文科省の歴史教育行政を支配していくことになる。それと日米構造協議などのアメリカの攻撃が明確な戦略を持って立ち上がってきたということも。
とにかくあの時代をふりかえり、現在の立ち位置をつかむためにも、たいへん貴重な本です。
ぜひ手に取ってご覧ください。

閑話休題。
ぼくは著者よりも3つほど年上だったみたいですが(ウィキ情報ですw)、三歳違いなのでほぼ年齢的には同時代を生きてきました。歴史情報戦における著者の活躍を追いかけてきた一読者に過ぎません。ただ音楽やミュージシャンに関する著者の記事や発言もとても好きです。
ぼくにとっての80年代(70年代のことも)のことを少し書きます。
前にも書いたけど、18歳で立命館大学史学科に入り19歳で中退して、その後10年、共産主義に覚醒した高校時代から「全共闘運動」への参加と共産主義への幻滅、反抗的人間への絶望等々という数年間の自分を何とか立て直すための長い勉強の時代に入りました。それがぼくの70年代でした。
就職はせず、5年間は日本自転車競技会(競輪)の審判員(最初はけがをした選手を運ぶアルバイトから)として、後半の5年間は小岩駅の弘栄堂書店の店員として生きていました。
自由にできる時間があることと、食べていけて必要な本が買えるくらいの最低限の収入があることが、この10年の基本方針でした。競輪場時代は月に16日の勤務で実働一日2時間、あとは何をしていてもよいという勤務でした。目的に完璧な仕事でした。本屋時代は普通に勤めましたが勤務時間中はかなり自由にさせてもらっていた不良社員でした。本が安く変えて読む時間もたっぷりありました。国鉄の子会社で店長さんものんびりしていましたね。
もうすぐ10年というところで子供が生まれることになり、長い浪人時代に終止符を打ちました。観念の生活に別れを告げてふつうの常識人として生きることにしました。が、肉体や手先の器用さにかかわる仕事にはまったく自信がなく、その結果ぼくくらいの三流の知性でもなんとかなりそうな教師の道を選びました。
本屋に勤めながら明星大学通信教育に入学したのが79年4月。教員免状をもらったのが81年3月。大学はまた中退して地元の教育委員会に行きました。履歴書があまりにもひどいので産休代用などがあってもなかなか雇ってもらえずしばらくお味噌の訪問販売をやりながら待っていました。
仕事をもらえたのが1年後の夏だったと思います。たった2週間でしたが「まじめふうに」シャカリキに働いて信用をもらいました。その後は途切れないで産休代用教員をずっとやっていました。試験が受からなかったからです。やっと採用試験に合格したのが1985年(昭和60年)でした(ピアノとか水泳とかたいへんでした)。
その後、藤岡信勝さんと出会うという幸運にめぐまれて、少しずつ甲斐のある人生になっていきましたが、それは当初の「常識のある生活者」という構想からはちょっとばかりはずれる生き方になってしまいました。まあそれはそれ。いつものように楽しいほうを選んできたわけです。その後も紆余曲折して今日があります。
ぼくにとって80年代は、前半が産休代用教員で後半が地方公務員の教員時代です。『授業づくりネットワーク』という教育雑誌の創刊にかかわり、その編集会議で月2回上京するほかはだいたい家と教室の往復でした。歴史教育に係るようになったのは1993年の「近現代史書き直しプロジェクト」からで、本格的には1995年の「自由主義史観研究会」からです。
80年代のおもな精神生活は日々の授業実践につきますが、しいて言えば東欧のソ連共産党への抵抗をウオッチし続けていました。ぼくのなかでは共産主義は完全な全体主義(ファシズム・ナチズムと同じ)になっていましたから、ポーランドなどの抵抗運動のニュースがぼくにとって最も重要な思想的な動きでした。唯一関心のある国際ニュースがこれでした。ワレサがポーランド労組の議長になったのが1980年頃でベルリンの壁が崩れたのが1989年でした。ぼくが考えることを始めたと意識したのは、高校のときのハンガリー動乱勉強会と大学の全共闘運動とプラハの春事件でしたから。つまり、ぼくにとっての1980年代とは、ソ連に支配された東欧諸国と共産党に支配されたソ連国民が自由を現実化する10年ということになります。
最後にこれは西村さんも書いていますが、焼野原の敗戦国日本を1980年代の「黄金時代」まで持ってきたのは、大正世代です。つまりぼくや西村さんの親の世代です。彼らはすすんで戦争に行って、「いい日本人は帰ってこなかった」と考えていた「生き残った日本人」でした。
彼らが精魂込めて戦った「復讐戦」の結果があの奇跡の経済成長でした。
上に書いたぼくの20代(70年代)の勝手な読書三昧の生活が可能になったのも、親たちの世代が成し遂げた経済成長・豊かさのおかげだったわけです。そう考えるとぼくの80年代はまさに仕方がない「蕩児の帰郷」だったとわかります。
失われた三十年とは昭和の戦争時代から戦後すぐに生まれた世代の日本人の敗戦であり、いまやほぼ現役を引退したこの世代の戦争責任(失われた三十年の)は重いものがあります。





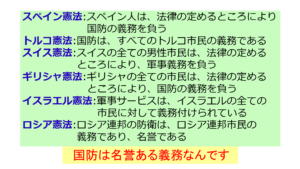






コメント