本居宣長の「からごころ(漢意)」は難しい。
長谷川美千子「からごころ」は丸ごとらえよう(哲学者的)としてかえって一面しかとらえられなかったという気がする。小林秀雄『本居宣長』はすべてを宣長に語らせる姿なので感動はあるが何かがわかったという読み方はできない。これらの名著と比べると、先崎彰容『本居宣長』は学究的で謙虚だ。ぼくの問題意識(歴史授業的)と重なる部分が多くよくわかるし役に立ちそうだ。それでもう十日になるが行きつ戻りつしながら楽しんでいる。
賀茂真淵から古学のバトンを受け取ったとき「漢意」とは儒教や仏教が考えていることだった。
勧善懲悪など、世界をとらえるための理屈(論理・倫理)などのことであり、それらの価値基準をさしていた。
「万葉集は『からごころ』で読まれてきたがそれでは古代人の心はわからないよ」というふうに。それは当時の知識人の身に沁みついた常識のことをさしていた。
宣長の「からごころ」にもそれはあるが、さらに一歩進んで「漢字で書き考えることから生まれてきたこと」という本質的な問題意識が含まれてことになった。漢字を使うしかなかったために、日本人に生まれた「漢字文明」的な思考のことだ。
それだけでなく、漢字という文字(漢字)の導入そのものが日本人にとってあらゆる思考の始まりであった、という原理的な問題を提起していた。これがあまりにも本質的な発見なので「難しい」のだと思う。
たとえばこういう記述がある(P265から引用)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「倭歌」を漢字表記に引きずられ「やまとうた」と訓読みしたとき、何が起きたのか。
これ以降、万葉仮名の「夜麻登」が「大和」と表記されるようになると、この「大和」から発想はどんどん飛躍して「日本はおおらかで調和を貴ぶ国なのだ」といった根拠薄弱な日本論が横行するようになった。「やまと」という音に「夜麻登」という表音漢字をあてていたとき、もちろん漢字それ自体に意味はない。だが表音文字だったはずの「夜麻登」を「大和」に書き換えたとき、無意識のうちに漢字の意味に引きずられ始める。大陸の文化圏の常識で、日本の古代世界を解釈してしまう。これと似たような積み重ねが、神道でも行われていった。
そのような事態に対して、今の神道家たちは古代を忘却していると批判したわけだ。(引用終わり)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「大和」という表記がどうして始まったのかを考えると上の後先は入れ替わるかもしれないが、音と訓の両方が必要だと決断した時点で、引用のような問題が生じてくるわけだ。長谷川美知子は日本人は漢字を意味の体系としては受け入れず単なる「情報システム」として借用した、というふうに論を進めたが、そう簡単ではないということがわかる。少なくとも宣長はそう考えていない。
★★★
大河ドラマ「光る君へ」を毎回楽しみに見ている。
紫式部らの宮廷の女性たちが男たちの「からごころ」を批判しながら「やまとごころ」を紡ぎだしていった革命的な時代だったことがよく伝わってくる。ドラマとしてもとても楽しい。
彼女たちの「やまとごころ」の文学の背景にも「漢籍」があり、シナの漢字文明は彼女らにとっても激しい憧憬の対象だったこともわかる。それでも生み出された物語は大昔から受け継いだ「大和心(もののあわれ)」になった。それは彼女たちの価値の中心が「天下国家的な世界」ではなく「男女の性愛的な世界」だからだ。
吉本隆明は国家・社会と家族では価値が逆立ちすると書いた。
家族では人間は「性」として存在して言えるが、国家・社会では人間は性的存在ではないからだ。両者では「いちばんたいせつなもの」が逆転してしまうのだ。
この国家観と家族観は、日本を考えるうえでとても重要だと思い始めている。
シナの漢字文明にさらされる以前の日本は、農耕・文字・国家という文明化した社会とは無縁だった(縄文時代)。
それは人間が家族(性的人間)として存在していた幸福な時代だったと考えることもできる。
先人はそこで命がけの飛躍をした。
日本はシナ漢字文明によって文明化し国家となることを選んだ。
それをしなければ現在の揚子江周辺の少数民族と同じ道をたどることになったのだと思う。
禍福は糾える縄の如しだ。




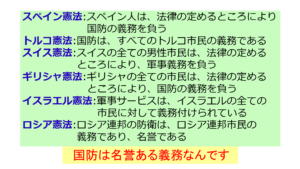




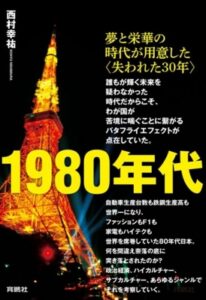

コメント