★中学校社会科には「公民」という科目があります。小学校社会科(6年)は「歴史分野:」と「公民分野」があります。
「公民」教育は「日本国民を育てるための教育」の一部で、おもに立憲政治・自由経済・国際関係などを通して日本国民の育成をめざしています。国民を育てるもうひとつの分野は「歴史」です。
★この投稿は、2/22「日本が好きになる歴史&公民授業セミナー」の藤岡信勝さんの講演「公民教科書の問題点」の資料にもとづいています。またこの資料の内容は小山常美さん(つくる会公民教科書執筆者代表)のブログにもとづいています。史料にもとづいていますが、ぼくの解釈や考え方も入っていますので、お二人の意図と違うところもあるかもしれません。諒としてください。
公民教科書の問題点(藤岡信勝)より
公民教科書の争点は7つあります。その7つの争点の概要を記します。
1 家族
・人間は成人するまでは家族の保護下で育つのが普通です。子供が初めて出会う共同体であり、家族なくして生存も自立して生きることはかないません。家族がない子供は地域社会や政府が支えるのが一般です。
・共産主義ソ連はかつて「家族は反動的な思想を植え付ける反動的な機関だ」として、これを否定しようとしました。たしかに家族は共産党とは独立しているので、思想に染まっていません。家族は伝統的な価値を継承する共同体ですから、共産党が危険視したのです.
それでレーニンは、赤ん坊が生まれたら家族から引き離して、政府が育てることにしたのです。
赤ん坊のうちから共産主義のゆりかごに乗せて洗脳しようとしたのです。
しかし結局それは失敗しました。赤ん坊を子供にし、子供を大人にする大事業は、家族にしかできないことがわかったからです。
・むかし教科書は家族について20ページ以上をさいてその大切さを説明していました。いまでも教育基本法は家族の大切さを書いています。
・しかし、平成22(2010)年度から、文科省学習指導要領から「家族」が消えてしまいました。いま、家族という単元を設定して、家族の大切さを教えている教科書は自由社と育鵬社だけになりました。
どうやら現代日本に新しいレーニンがいるようです。
争点2 公共の精神
・教育基本法には「公共の精神」の育成が日本の教育の目標として書かれています。
・「公共の精神」は、自由主義的・民主主義的な国家および地域社会を支える国民必須の精神です。
しかし、文科省の学習指導要領にも各社の教科書にも「公共の精神」に関する記述がありません。書いているのはやはり自由社と育鵬社だけです。
・自由社はこう書いています。
「地域社会と公共の精神」
「個人や家族の生活は、地域社会とともにあり、地域社会の支えがあって初めて成り立ちます。そのためには公共の精神が必要です」「公共の精神とは、自のお利益や権利だけでなく、社会全体の利益と幸福を考えて行動する精神のことです」「個人として自由に生きる側面とは別に、公共の精神の持ち主としての観点から見た個人を公民と言います。
公民と個人のバランスが取れた人が、地域社会の発展に貢献できる人です」
争点3 愛国心
・教育基本法には「わが国と郷土を愛する」ことを日本の教育の大目標に掲げています。文科省の学習指導要領にも公民的分野の目標に「自国を愛し」とい言葉があります。
しかし、7社中4社の教科書にはこれがなくそれでも検定を合格しています。書いているのはまたも、自由社と育鵬社だけです。
・自由社の教科書から引用します。
「生まれ育った祖国を大切に思う心を愛国心といいます。オリンピックで日本の選手が活躍したときにうれしくなるのは、愛国心の自然な表れです」
「故郷をいとおしく思う愛郷心(郷土愛)、そして愛国心は自然な感情として芽生え育っていくものです」
「同じ国家に属するという共通の意識から、国民は一体感をもつことができます。そして先人が懸命に伝えてきた伝統・文化や連綿と続く歴史に対する理解が深まると国家・社会の発展のために努力していこうという気持ちが自然と養われていきます」
・愛国心を国民としての尊い心として教えない教科書が4社あり、教育基本法違反が明確であるのに文科省の検定を通ってしまいます。そしてその4社の教科書で日本の中学生の95%がまなんでいます。教育基本法を守っている自由社と育鵬社の教科書はほとんど採択されません。
・愛国心という言葉にアレルギーのある人々がいるのはわかります。
愛国心が暴走すると危険な場合があることは、近現代の歴史を学べばわかるからです。
しかし、自由社や育鵬社の教える愛国心は、決してそのようなファナティックなものではなりません。冷静で合理的で健康な愛国心です。
逆にこれを教えず忘れさせる教育の危険を考えるべきなのです。
立憲君主制を採用するわが国は国民主権をうたっています。国の政治の主権者が、祖国をわが事(自分事)と思うその心が愛国心です。
それが欠如していたら、個人は根無し草でありとうてい国家の主権者になることは出来ません。
主権者がしっかり支えない民主主義が専制主義・独裁国家の方に行きやすいことは、これも歴史が教えるところです。
自国を支え、より良い国にしていこうと思える国民を育てるのが、まさしくこの健全な愛国心です。教育基本法も学習指導要領もともにそういいう同じ心に立っています。
愛国心の暴走を恐れて「愛国心を丸ごと捨ててしまうこと」こそ誤りなのです。
そろそろ当たり前の「常識」に還るときではないでしょうか。
自由社と育鵬社の教科書に学びましょう。教育基本法の心に学びましょう
(つづく)





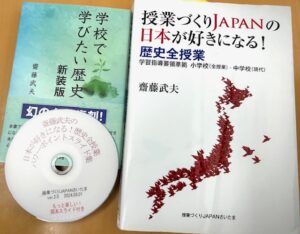

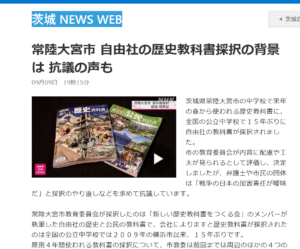


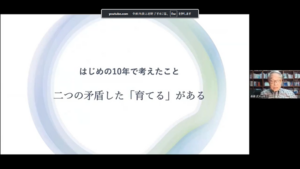

コメント