ぼんやりしたテーマで書き始めて、あっちこっちしてきてしまいましたが、ようやく自分が考えていたこと&考えていることが少しずつですが見えてきたような気がします。この後は各論になると思いますので、大きな風呂敷を広げたまま来てしまったこの連載をいったん閉じることにしました。
このようないい加減なものでも、投稿すると40人くらいの方が見てくださっていました。感謝の思いしかありません。ありがとうございました。
ただ、「日本の未来を支える子供のための授業をつくる」という教育の現場思考で歴史と国の在り方を考えてきた意味はきっとあると考えています。そして、ぼくがいまいる立場はこれまでの知識人はだれも言っていないような気がしています。日本にとって大事なことだと思うのでこれからも少しずつ掘っていこうと思います。
自由主義史観研究会(藤岡信勝代表)は発足(1995)のときからメディアからは右翼あつかいをされてきました。いまフランスのルペンなどが「極右」とされていますが、内藤さんが仰るようにルペンは「ドゴール主義(フランス第一)」でしょう。ドゴールは「極右」だったのでしょうか。ありえません。それと同じように、自由主義史観研究会はその名の通り「自由主義」の立場を守ったと考えています。いわゆる古典的なリベラルの立場です。反全体主義(反共産主義・反ファシズム・反専制主義・反右翼・反左翼)です。個人の自由に最も価値を置くとともに、個人の自由を現実化するために不可欠な国家・共同体にも価値を置く立場です。
ぼくは自由主義史観研究会の機関誌創刊号(1995年9月)に「われわれの物語をどう構想するか」という巻頭論文を書いています。そこにこういう一節があります。
「昭和初期の軍部特に青年将校の思想、農本主義者の思想、共産主義者の思想、革新官僚の思想(転向した共産主義者)など、これらすべてを「自由主義の否定」という水平面において検討すること。これらはすべて「啓蒙主義」(堺屋太一)の政治思想である。
産業化に対する態度と皇室に対する態度で仕分けできるこれらの政治思想は、前述した啓蒙主義的な政治制度(独裁・専制・統制経済)で日本を救済しようとした点でほとんど等価である。これに対中・対英米・対ソ連という選択肢が絡まる。
当時の国民の多くは、腐敗した政党政治家やハイカラな自由主義者よりも、彼らが描く全体主義的な政治に期待していた。そこにこそ現実的で有効な変革の可能性を見たのである。資本主義・自由主義には国民を動かす「憂国の志」が見えにくい構造があるようだ。
それは自由主義の倫理が「自由な個人」という理念に依拠しているからだろう。これは私たちの国の信仰からは最も遠かった倫理の型かもしれない。
この国で「自由な個人」という理念が可能かどうかは、今もなお私たちの課題である」
自由主義史観研究会に参加したときぼくは、大東亜戦争期の「右翼」は「左翼(革新官僚)」と同じだったと考えていたことがわかります。そして、右翼的な尊王家ではなく、合理主義的な自由主義的な尊王家をめざしていました。その立ち位置は現在も変わっていません。
「日本が好きになる!歴史授業」はそういう立場で構想され実践されてきました。
これまでは、「日本が好きになる!歴史授業」を普及させたいという思いが先行して、この授業が「反右翼」であることをややあいまいにしてきたところがありました。反省しています。
ぼくは、大東亜戦争の運命についてはつとめて共感的にとらえてはいますが、当時の指導者たちが自由主義的な立場の知識人や国民をきびしく弾圧していたことは否定的にとらえています。それはきわめて反自由市場経済の思想でした。この傾向が現在も今後も日本を支配する可能性は大であると思われます。これを心して監視しなければなりません。日本の知識階層にある「天皇制への甘え」(これは左右両者にあります)を克服する道を探っていきたいと考えています。
今日書いたことはこれまでのぼくの支持者のみなさんには理解できない点が多々あるかもしれません。また自分自身でもまだ十分には明確になっていないところがあります。
舌足らずの所はお許し下さい。今後もあきらめずに勉強していきますのでどうぞよろしくお願いします。





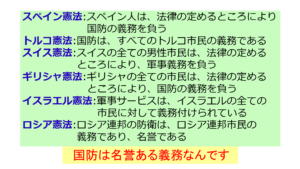
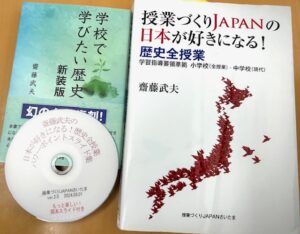
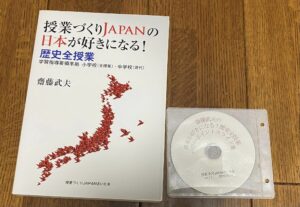
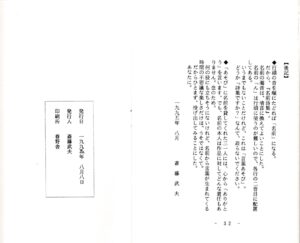
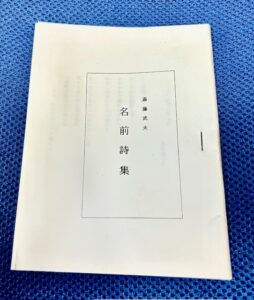

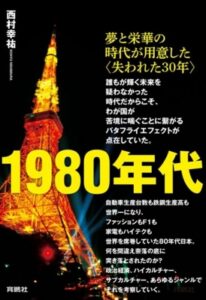
コメント